 |
 |
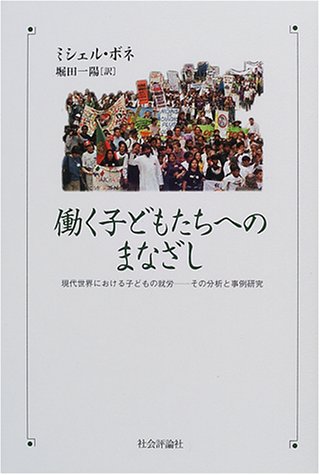
|
●ミシェル・ボネ著
『働く子どもたちへのまなざし
現代世界における子どもの就労――その分析と事例研究』
◆堀田一陽訳
◆社会評論社刊
【訳者の堀田一陽氏によるこの本の紹介】
本書は「常に闘いの現地に立つ活動家にして、ILO国際労働事務局の専門官」、「反児童労働の疲れを知らぬ闘士」(『ル・モンド』紙)ミシェル・ボネ氏が、その豊富な体験をもとに働く子どもたちをとりまく現実と働く子どもたちへのまなざしについて縦横に語ったものである。
「わたしは 25年間に五つの大陸を歩いてきましたが、働く不幸な子どもたちよりももっと多くの働く幸せな子どもたちに出会いました。子どもたちは働くことに誇りをもち、たった一つの恐れを抱いています、仕事を失う恐れです。もちろん、子どもたちは労働条件をもっと厳しくないものにしてほしい、もう少し多く稼ぎたいと思っています。実際、それは普通の労働者の要求そのものです」
インタビューに答えるボネ氏の言葉である。
ひとりの働く子どもの顔を見いだすとは、ひとりの働く子どもを本当に発見するとはどういうことかとボネ氏は問いかける。そのためにはまず、働く子どもたちの生きた多様性に注目してほしいと。
インド、デリーから車で 2時間ほどの小さな町ギュルガオンで、5歳の砕石工バリュは 11月の夜明け前の湿った寒気をまぎらそうと貧弱なたき火に手をかざす。炎天下、干し草とこねてクッキー状にし、日干しして燃料にするために、道路で牛糞を集めていたバブは 10歳、あるいはインドのシリコンバレーとも呼ばれる近代的な大都市バンガロールで、くず拾いサライ、12歳の少年は児童指導員に秤の見方を習った。「すっかり変わったよ。紙やくず鉄を売るとき、ぼくは秤の針がどこにあるか、ちゃんと見るからね、もうぼくをだませないよ」。そしてコロンボ郊外の小さな町で、国連主導の子どもの権利条約の意識化運動の子ども集会を抜け出し、れんが工場の機械を自分たちだけで動かしてみせたスリランカの、15歳を頭にしたれんが工たちは言う、「国連に、働きたがっている子どもたちを工場から追い出してはいけないって法律が必要だって言ってよ。それにもう一つ、働いているときでも少しは勉強ができる法律が必要だ、ともね」。
本書で、ボネ氏はIPEC(児童労働撤廃国際プログラム)やアフリカ地域の国際計画、児童の債務奴隷に反対するプログラム、また 1998年の「児童労働に反対するグローバル・マーチ」(フランス側統括責任者)を担当した経験から、児童労働と児童の搾取を形成している世界システムを分析している。一方により多くの利益を求める社会と社会階層、他方には極端な貧困にあえぐ家族、社会階層があり、この両者のあいだに子どもの斡旋屋、運び屋などの仲介人たちが暗躍する世界、政府、雇用者の戦略、NGOのさまざまな取り組みを一つひとつ読み解いてゆく。
1996年、インド南部の町クンダプールで、アジア、アフリカ、ラテンアメリカ、33カ国から集まった働く子どもと若者の国際会合が開かれ、クンダプール宣言としてまとめられた。
第一条.ぼくたちわたしたちは、みな、ぼくたちわたしたちの問題、ぼくたちわたしたちのイニシアティブと提案、ぼくたちわたしたちの組織過程を認めるよう望みます。
第二条.ぼくたちわたしたちは、子どもたちによって生産された製品のボイコットに反対します。
第三条.ぼくたちわたしたちは、ぼくたちわたしたちの労働に対して敬意が払われ、その安全が確保されることを望みます。
第十条.ぼくたちわたしたちは、ぼくたちわたしたちの労働を搾取することに反対しますが、ぼくたちわたしたちの教育と余暇の楽しみに適う時程をもった品位ある労働に賛成します。
世界の働く子どもたち、若者たちの要求の精華こそ、この十条から成るクンダプール宣言である。グローバル化の名のもとに世界経済秩序に逃れようもなく組み込まれている働く子どもたちとともに歩むとは、わたしたち一人ひとりが生活そのものを見つめ直すことであると、このクンダプール宣言が示している。(「第2回働く子どもおよび若者による国際会合」は 2004年 4月にベルリンで開かれた。世界3大陸から 30名の働く子どもたち、若者たちが参加し、第1回クンダプール会合のフォローアップと国際条約および国際運動に対する意思表示などがおこなわれた。)
「あなたは児童労働の決定的な撲滅を求めないのですか」と問われたボネ氏はきっぱりと答える。
「求めません! 児童労働の撲滅を達成するには 50年かかります。児童労働の撲滅については、それが有益かどうかを見極める必要があります。あの子どもたちは仕事をとりあげられたら、どうするでしょうか。夢を見ていてはいけないのです。実現可能なこと、子どもたちも、その家族も望むこと、それは子どもたちを保護された部門で、しかも学業と並立させられる条件で働かせることです。」
そして最終章では、わたしたちがひとりの働く子どもの手をとるとはどんな行為なのだろうとボネ氏は自問する。
社会におけるわたしたちの位置や働く子どもたちとの関係や物事の見方がどうであれ、わたしたちはみな、働く子どもたちの背後に共通して在る「なにものか」を予感している。わたしたちは本書を通してその「なにものか」に近づき、見届け、名付けようとしてきた。わたしはそれを暫定的に「児童労働」と呼んでいるが、しかし、児童労働とはわたしたちの心に取りついている一種の幽霊ではないか、子どもの頃、震えながら聞いた幽霊屋敷のお話しに出てくるあの幽霊のようなものではないか。児童労働の廃止に向けた数限りない政策、条約、行動計画が実行され、今も実行されつづけているのは、この社会現象への取り組みに恐怖感が支配しているからではないのか。まるでわたしたちの熟考や言説の回廊の一本一本を、しかと目には見えるが掴みどころのない、それゆえに危険な幽霊がさ迷い歩いているようなのだ。つまり児童労働はわたしたちにとって危険なのだ。
子どもを小学校へやったり、企業に労働監査官を立ち入らせたり、製品に保証ラベルをつけさせたりするのは簡単だ。わたしたちはそうしている。しかし、うまくいっていない。子どもたちは相変わらず仕事についている。幽霊は徘徊しつづけ、わたしたちの恐怖心は払い除けられないでいる。
働く子どもたちの脳裡には夜も昼もあの、なぜ、なぜ、なぜという疑問がとりついている。なぜこんなにきつい仕事をしなければならないの? なぜ少し働いて少し学校へ行くことができないの? なぜこんなに給料が安いの? なぜ貧しいぼくたちには社会は不公正なの? 働く子どもたちのなぜには回答もなく、邪悪な力をもった幽霊が取りついているとの感じだけを残してゆく。だとしたら、働く子どもたちとともに歩くとは、働く子どもたちに、子どもたちの疑問への回答として働く子どもたちに関係ある行動に参加するよう提案することではないのか。
働く子どもたちは世界の政治的、経済的、文化的重圧の下にあり、ヨーロッパにいるわたし(日本にいるあなた)たちはその世界の主人だ。わたしたちはすばらしい権力をもっている。その「武器」は国の政策、労働組合、国連、世界銀行だ。これが偽りの解決策で効果がないなどと言うつもりは毛頭ない。わたしはただ、それが働く子どもたちが望んでいる回答だとは思わないのだ。
大事なことは、わたしたちが持っていて働く子どもたちが持っていない富や権力を基礎に置くのではなく、働く子どもたちとのパートナーシップを基礎に置き、子どもたちの疑問への回答や行動計画を作成することではないのか。
この意味で、わたしたちが働く子どもたちにそそぐまなざしは、働く子どもたちとのわたしたちの関係システムを逆転させ、と同時に、許しがたい搾取を目にしてわたしたちの内部に湧きおこった怒りは変じて、より高度な価値へと移るだろう。そうすれば、わたしたちは歴史の中心的現実としての、新たな労働をも見いだすだろう。
本書をとおして、あなたにとっての一人の働く子どもとの出会いがあれば……。
|
|
 |
|
 |
JFSAの活動は会員の方々に支えられています。
会員になるには下記の郵便口座に年会費をお振込みいただくか、 直接JFSA事務局まで直接お持ちください。
●2017年度(2017年10月~2018年9月)分の会費になります。
●会員(正会員)には総会の議決権があります。
●会員、支援メンバーには年3回の会報と、 年1回サポーターグッズ(アルカイールの生徒が作ったものなど)を郵送いたします。
※サポーターグッズのサンプルはこちらからご覧ください。
◆郵便振替口座番号 00160-7-444198
◆加入者名 JFSA
≪年会費≫
【 会員(正会員)】
個人1口\5,000-/団体1口\50,000-
【 支援メンバー】
個人1口\2,000-/団体1口\10,000-
※通信欄に「会員」または「支援メンバー」、「個人」または「団体」、口数をお書き添えください(郵便振替用紙サンプルはこちらからご覧ください)。
※カンパ金をご入金いただく場合も上記口座をご利用ください。通信欄には「カンパ」とお書き添えください。 |
|
 |
 |
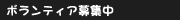 |
| |
 |
JFSAでは活動を支えるボランティアを募集しています。
【作業内容】
①和服の選別、ハギレ作成、値段付け、など
②寄付された切手などの整理。
③会報などの郵送準備作業。
④パキスタンへの古着コンテナ詰込み作業など。
⑤フリーマーケットやチャリティ古着バザールなど古着販売に関わる補助作業。
【作業日】
作業内容により異なります。JFSA事務局へお問合せください。
【作業場所】
⑤以外はNPO法人JFSA事務局で行います。
*参加ご希望の方はJFSA事務局までお気軽にお問合せください。*ボランティアは無償で、交通費などの手当てもありません。ご了承ください。 |
|
 |
 |
 |
|
 |
【NPO法人JFSA事務局】
住所:〒260-0001
千葉市中央区都町3-14-10
業務時間:10:30~19:00
(木曜定休)
電話/FAX:043-234-1206
E-mail:jfsa@f3.dion.ne.jp |
 |
|
|
|
|
|
 |
